ななちゃん「後見人って、認知症になってから決めるって聞いたけど」
スズ「後見人って、二種類あるねん」
ななちゃん「そうなん?」
スズ「法定後見人っていうのは、認知症になってから決められるねん」
ななちゃん「うん」
スズ「任意後見人っていうのは、元気なうちに『私が認知症とかになった時はよろしくね』って先に決めとくねん」
今日は、「法定後見制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
任意後見制度では、
自分が元気なうちに
「私がこの先、認知症などで判断力が低下したら、財産管理などをお願いします」と、
任意後見人を決めて契約を交わします。
ただし、
契約を結んでも すぐに効力が生じるわけではありません。
認知症などで判断力が低下した時点で、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任すると
任意後見人が財産管理などを行えるようになります。
さて、
後見人には
「任意後見人」と
「法定後見人」の二種類あります。
任意後見人は、先ほど述べたように
「自分が元気なうちに」決めておきますが、
法定後見人は、
「自分が認知症などで判断能力が不十分になった後」に、
親族などの申し立てを受けて
家庭裁判所が選任します。
「家庭裁判所が選ぶの…? 自分で決められないの?」
そうなんです。
法定後見人は自分で決めることはできません。
家庭裁判所が適当と思われる人を「選任」します。
では、
どういった経緯で「法定後見人」は選ばれるのでしょうか?
Aさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは一人暮らし。
離れて暮らす子(Bさん)が時々顔を見に来ますが、
最近、冷蔵庫の中にヨーグルトが大量に入っていることに気が付きました。
お母さん(Aさん)に尋ねると、
「もう無くなったと思って買ったら、冷蔵庫に入ってた」と言います。
さらに、
貸金業者からお金を借りた際の書類も見つかり
Bさんはお母さんのことが心配になってきました。
そこでBさんが家庭裁判所に申し立てをしたところ、
家庭裁判所はBさんを「法定後見人」に選任しました。
さて、
この場合
家庭裁判所に申し立てをしたBさんが
「法定後見人」に選ばれましたが、
全く別の第三者(弁護士や司法書士などの専門家)が
選ばれる場合もあります。
ななちゃん「知らん人が選ばれたらいややな」
スズ「そうとも言える」
今日は、「法定後見制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「財産管理等委任契約」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
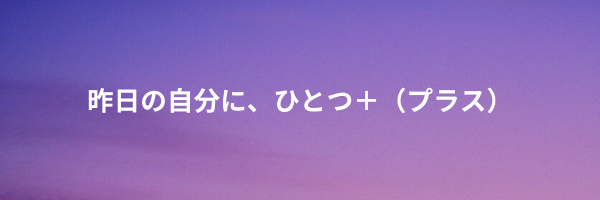



コメント