ななちゃん「後見人制度ってさ、いろいろあるやん」
スズ「いろいろ?」
ななちゃん「法定後見とか任意後見とかさ」
スズ「そやね」
ななちゃん「何が違うんやったっけ」
今日は、「任意後見制度のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
任意後見制度は、
自分の判断力が不十分になったときに備えて
あらかじめ信頼できる人に
生活や財産の管理をお願いしておく仕組みです。
特徴は
「まだ判断力がある元気なうちに、誰に頼むかを決めておける」という点です。
利用するには、
公証役場で「任意後見契約」という公正証書を作成します。
さて、
任意後見人としてお願いできるのは、
家族はもちろん
弁護士や司法書士などの専門家でも構いません。
契約内容も、
自分の希望に応じて比較的柔軟に決められます。
たとえば
「財産管理だけをお願いする」
「介護や医療の契約も含めて幅広くお願いする」といったように、
自分の将来の生活設計に沿って契約内容を決めることができます。
公正証書作成の際には、
手数料が必要で
契約内容によりますが おおむね数万円(2万~4万円程度が多い) がかかります。
ただし、
契約を結んだだけでは効力は発生しません。
実際に本人の判断力が低下し、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときに
初めて契約がスタートします。
この監督人が任意後見人を見守り、
契約が守られているかをチェックします。
監督人には毎月 1万~3万円程度の報酬が
本人の財産から支払われ
金額は家庭裁判所が決定します。
任意後見制度の大きな利点は、
「自分で選んだ人に任せられる安心感」があることです。
一方で、
公正証書作成や
監督人への報酬といった費用が必要になる点は理解しておく必要があります。
ななちゃん「家族が後見人になれるんや」
スズ「うん」
今日は、「任意後見制度と費用のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「土地購入にかかる費用」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
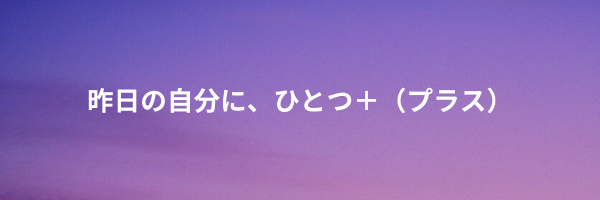



コメント