ななちゃん「同僚のお父さん、認知症が進んじゃってるねんて」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「最近は、自分でいろいろ決めることもでけへんようになってきたって」
スズ「そっか」
ななちゃん「お金の管理とかももう無理かも、って」
スズ「そうなんや」
今日は、「法定後見制度と費用のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
成年後見制度は、
認知症や知的障害などで判断する力が十分でなくなった人を
法律的に支える仕組みです。
大きく分けて「任意後見」と「法定後見」がありますが、
ここでは「法定後見」について見ていきましょう。
法定後見では、
「誰が後見人になるか」を家庭裁判所が決定します。
家族が「自分がやりたい」と希望しても、
必ず選ばれるとは限りません。
弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることも多く、
その場合は毎月の報酬を本人の財産から支払う必要があります。
報酬は財産の額や事務の内容によって異なりますが、
一般的には月2万円から5万円程度で
最終的な金額は家庭裁判所が決定します。
後見人の役割は大きく二つあります。
一つは「財産管理」で、
預貯金や不動産を守り
必要に応じて医療費や生活費に充てることです。
もう一つは「身上保護」といって、
介護サービスや医療、施設入所の契約など
本人の生活や療養に関わる判断をサポートすることです。
いずれも「本人のためになるかどうか」が基準であり、
そのため家族が出金をお願いしても
本人に直接利益がなければ認められない場合があります。
また、
一度始めた法定後見は途中でやめることはできず
制度が終了するのは本人が亡くなった時などに限られます。
「合わなかったら解約」という使い方はできません。
このように法定後見制度は、
本人の財産と生活を守る強力な仕組みですが
家族にとっては制約や費用負担を感じることもあります。
利用を検討する際は、
事前に備えられる「任意後見」や「民事信託」とあわせて考え
専門家に相談することが安心につながるのではないでしょうか。
ななちゃん「お金かかるんや」
スズ「そやね」
今日は、「法定後見制度と費用のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「任意後見制度と費用のしくみ」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
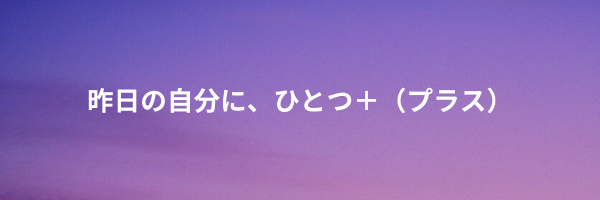



コメント