ななちゃん「おばさんがさ、『認知症になったらどうしよ』って言ってる」
スズ「そうなんや」
ななちゃん「今でも、契約書見たりするの大変やのに、認知症になったら絶対できなくなるって心配してる」
スズ「なるほど」
ななちゃん「自分ででけへんようになったらどうしたらいいの?」
今日は、「任意後見制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう
ななちゃんのおばさんは、
この先認知症になってしまったら
自分でいろいろ決めることができなくなるんじゃないかと心配しています。
では、
Aさんの場合を見ていきましょう。
Aさんは70歳。
一人暮らしです。
今は生活するのに困ることはありませんが、
この先もし自分が認知症になると、
「いろんな手続きができなくなるのでは…」
「お金の管理ができなくなるのでは…」
と心配するようになりました。
そこで、
「後見人がいれば安心」という話を聞いたことがあったので、
後見人について少し調べてみました。
それによると、
「財産などのことを任せる人(後見人)」を自分で決めることができる
ということが分かりました。
Aさんは一人暮らしですが、
仲の良い姪がいます。
Aさんは、
「自分が認知症になったら、姪に財産などのことを任せよう」と考えました。
Aさんは姪と話をして、
この先認知症などで判断能力が低下した時に備え
今のうちに姪に「任意後見人」になってもらう契約を結ぶことにしました。
(契約は公正証書で作成します)
このように、
自分で後見人を選ぶ制度を
「任意後見制度」と言い、
選ばれた後見人を「任意後見人」と言います。
将来、Aさんが認知症になった時には
家庭裁判所に申し立てて
姪が「任意後見人」となり、
同時に「任意後見監督人」が選ばれることになります。
「任意後見監督人」の役割は、
任意後見人が適正に仕事をしているかを監督することで、
家庭裁判所が選任します。
ななちゃん「監督されるんや」
スズ「(笑)」
今日は、「任意後見制度」の知識をひとつ+(プラス)しました。
明日は、「法定後見制度」の知識をひとつ+(プラス)していきましょう。
独立系ファイナンシャルプランナー事務所 FP office Bellsへのご相談は、
こちらから
https://fp-office-bells.com/contact.php
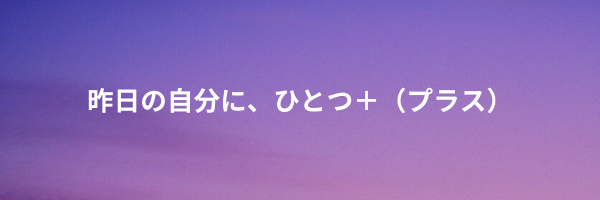

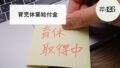

コメント